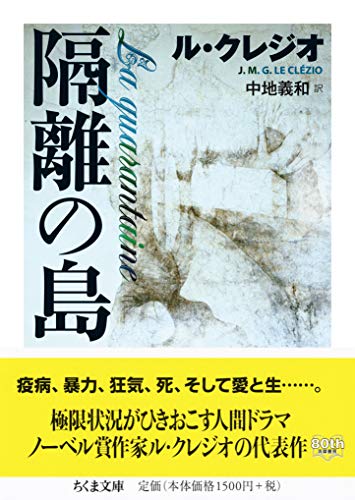もしも自分のこの足の裏が死んでいった人々の灰を、あるいは毀された多くの物を踏んで歩いているとしたら、そのことに私は耐えることができるだろうか。この本が私にとって本当に大事なのは、痛みで「土地」と繋がることを教えてくれるからだ。
J.M.G・ル・クレジオ著、中地義和 訳『隔離の島』(筑摩書房、2013年)
(文庫版が出ているとのことで嬉しいです。たくさんのひとにこの物語が届きますように。このブログ記事で引用するのは文庫版ではありません。予めご了承ください。)
ル・クレジオの他の作品についてはいくつかブログに感想を書いてきたけれど、この作品についてだけはどうしても、まだ、何も書くことができないままでいた。それはブログに感想を書くということが、私にとって、その本との距離みたいなものを決定づけてしまう行為だったからだ。それが怖くもあり、勿体ないことだと思う感情もあって、これまで感想を書かないでいた。大好きなこの本をいつまでもずっと漂うように読んでいたかった。それが今回この記事を書こうと思ったのは久しぶりの再読を経て、この本がどれほど自分に影響を与えていたかを知ったのと同時に、いつか私自身も自分の生きる土地に繋がることができたらいいのにと願ってしまったからだ。
自分のなかにあの亀裂を抱えていることは、いつだってわかっていた。それはひとつの痕跡、復讐への嗜好のように、誕生の瞬間に自分に与えられたものだった。
(前掲書、445頁より引用)
1980年の夏、それがこの小説の現在の時間だ。小説の語り手「ぼく」ことレオン・アルシャンボーがモーリシャスへ飛び立つ前の週に、かつて祖父がランボーに遭ったというカフェを探したパリの六月から、モーリシャスへ辿りつきアルシャンボー家の末裔であるアンナに会う同年八月までの時間。しかしこの「現在」には語り手「ぼく」によってとても多くの「時」が放り込まれている。たとえば1856年1月、カルカッタを発ったハイダリー号の船上で天然痘とコレラが発生し多くの移民がプラト島に置き去りにされたこと。1857年のセポイの大反乱の最中にカーンプルで殺された乳母の胸から拾い上げられた赤ん坊のアナンタとギリバラが、移民としてモーリシャスに辿りつくまでの旅の軌跡。1872年の1月か2月、語り手の祖父ジャックがまだ小さな子供だった頃、サン・シュルピス街のカフェでランボーに出会ったこと。そして小説中もっとも多く語られるのは1891年、語り手の祖父ジャックとその妻シュザンヌ、弟レオン(語り手とは別人)の船旅とプラト島での検疫隔離の日々。
この長い苦難の「時」を語るのはすべて「ぼく」(1980年のレオン)だ。だから、語られていることのすべてが事実として正しいかどうかはわからない。わからないけれど、「ぼく」にとっては正しいか正しくないかはあまり問題ではない。自分のなかに抱えている「亀裂」を乗り越えて多くの「過去」と「現在」を繋げることのほうが重要なのだ。そのために「ぼく」は過去を想起し、創造し、語る。過去の時を次から次へ現在に放り込んでいけば、〈時〉にふくれた現在は「永遠」に近づきはしないだろうか。それはとても豊かな時間の経験だ。
1891年、モーリシャスへ向けて始まった船旅は途中の些細な寄り道のせいで天然痘を道連れにしてしまい、「ぼく」の祖父とその妻、そしてもうひとりの「レオン」を含む多くの乗員が検疫隔離のためプラト島に置き去りにされてしまう。彼らが経験した死と隣り合わせの日々が最も長く濃密に語られている本書だが、それは「ぼく」が「レオンになる」ことで経験された時だ。つまり「ぼく」の創造を含んでいる。すべてが本当かどうかはもうわからない。何せ「ぼく」とは別の、もうひとりの「レオン」は検疫隔離の後で失踪してしまうのだ。「ぼく」は祖母シュザンヌにきいた話を反芻し、時には付け足しもして、物語る。まるで過去が生き直されるかのように。そしていつしかふたりの「レオン」は混ざり合い、1891年のレオンが現在の語り手にぴったり重なって、悪夢のような隔離の日々はほとんど現在形の物語として立ち現れる。
プラト島には大勢の移民たちが暮らしていた。彼らのことを忘れてはいけない。「なぜ神様は、どぶに住まわせるためにこの顔とこの身体をわたしにくれたの?」(325-326頁)と言う女性がいた。「そしてまたも、海に沈められる遺体の重たい音、その上にふたたび閉じる海の音」(332頁)がきこえた。読者はインドからモーリシャスを目指す移民の一団をギリバラとアナンタの物語に見ることになる。これが本書のもう一つの物語として、作中の時間に厚みを持たせている。
大勢の移民たちがモーリシャスという島にやって来ていた。そこには製糖工場があって、サトウキビ畑では多くの移民たちが働いていた。現場監督の不条理な暴力があったかもしれない、病気や貧困のせいでひどくつらい人生がいくつも消えていったかもしれない。
語り手「ぼく」はついに辿りついた現代(1980年)のモーリシャスを踏みしめて思う。「この島のいたるところで、人はインド人労働者たちの灰の上を歩いている。」(415頁)そうして「ぼく」が考えたことは、永久に流謫の境遇にいると思っていた自分がこのモーリシャスに結ばれているということだった。ここで「ぼく」が抱えていた「亀裂」は埋められて、遠い過去の存在と今現在の自分が繋がるように思えたのだ。それが、たくさんの物語を現在に投げ込み、時には失踪者「レオン」になったりもしながら、辿りついた結論だった。語り手「ぼく」は、移民たちの悲惨さまで含み込んだ「時」という、本当なら忘れてしまったほうがいいような流謫や流血の記憶までも思うことで、ようやくこの「土地」に繋がったのだ。
私は時々、自分が「ここ」北海道にいることを不安に思う。「ここ」がどういう場所なのか、私はよくわかっていない。「ここ」は明るい観光地のようでも、広大な墓地のようでもある気がする。子供の頃、親の仕事の都合で何度か引っ越しを経験した。小学校だけで三校も知ったけれど、いつも自分は転校生だった。そのせいか、何の疑いもなく「ここ」に根をおろして生きていく、という感性に乏しい。本当は故郷が欲しい。「ここ」を故郷だと思えたらそれはどんなに幸せなことだろう。そのために、私の足の裏は多くの痛みを踏むことがきっと必要なのだ。本当は忘れてしまったほうがいいのかもしれない、かなしみを思うことを忘れないように。
ル・クレジオほど、大きな物語でなくてもいいのかもしれない。世界史に繋がるような大事件にこの身を巻き込む必要もないのかもしれない。この本を大切に思う私は、語り手「ぼく」がモーリシャスという島に、自分がちゃんと繋がっていたと思えるようになったことが嬉しい。まだ子供だった祖父ジャックを射たランボーの暗い青いまなざしが、祖父を通り抜けて「ぼく」まで貫く、文学的夢のような想念が世代を繋ぎ物語を語る。土地から一掃されそうな負の記憶をまるで「今」あるものとして手にとるみたいに語り直すことで、「ぼく」という存在は確かにモーリシャスに繋がっているのだ。それは土地を踏みしめる足の裏に、死者の気配を感じることでもある。
--------------------------------------------------------------
※今月7日発売の「文學界」4月号エセ―欄に「末裔の足裏」という随筆を書きました。併せてお読みいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
(久栖)