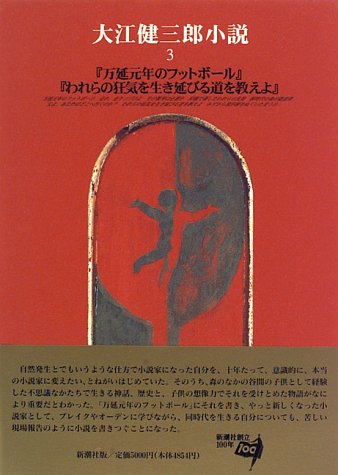「白いものについて書こうと決めた」と、始まる本書に最初に表れる白いもののリストはひとりの人間が生まれてから死ぬまでの時間に含まれ得るものだと思った。「おくるみ、うぶぎ」から「壽衣(註:埋葬の際に着せる衣裳)」までの時間。けれど読み進めていくと著者の文学の言葉が復元していくひとりの人間は、生まれてからたったの二時間で死んでしまったことがわかってくる。たったの二時間、言葉さえ覚える間もなく死んでしまった人間に、あの白いもののリストは長すぎる。けれど、著者の言葉はかつてナチスドイツによって破壊された都市(ワルシャワ)を歩くことで、存在することのなかった人の時間を可能にする。「私」は「彼女」に自分の生と体を貸し与えるのだ。
ハン・ガン著、斎藤真理子訳『すべての、白いものたちの』(河出書房新社、2018年)
(文庫本になっていたのを知りませんでした!私が持っているのは単行本のほうだったので引用ページ番号などは、単行本のものです。)
韓国語には白い色を表す言葉に、綿あめのようにひたすら清潔な白「ハヤン(まっしろな)」と、生と死の寂しさをたたえた色である「ヒン(しろい)」がある。本書の最後にあった「作家の言葉」という著者のあとがきで読んだ。著者が書きたかったのは「ヒン」についての本だったそうだ。そして本書はまさにそういう本だった。もう少し言えば生と死の間に浮かぶ1枚の白いガーゼのようなものが、私には思い浮かぶ。
単語を一つ書きとめるたび、不思議に胸がさわいだ。この本を必ず完成させたい。これを書く時間の中で、何かを変えることができそうだと思った。傷口に塗る白い軟膏と、そこにかぶせる白いガーゼのようなものが私には必要だったのだと。
(単行本、9頁より引用)
単語というのは、ブログの冒頭で紹介した「白いもののリスト」のことだ。「傷口に塗る白い軟膏と、そこにかぶせる白いガーゼのようなもの」という言葉のイメージが、今回再読をしていくなかでずっと印象に残り続けた。そういうものが「私」には必要だったと書きつつも、白いガーゼをかぶって隠れてしまってもいいのかと自問する。そして早々に「どこかに隠れるなどとはしょせん、できることではなかった」と悟る。
「私」が「あの冬を過ごすため」に借りた部屋へと通じるドアが忘れられない。「私」の前にこの部屋を借りていた誰かに、錐のような尖ったもので引っ掻かれて「301」という部屋番号が刻印されたドア。「乱暴に引かれた直線も曲線も赤黒く錆びた傷となり、傷跡から錆び水が垂れ落ち、古い血痕のように固まっている」ドア。「私」はこの上から刷毛で白いペンキを塗る。傷を覆い隠すガーゼのように。傷に触れるのは、こわい。だからガーゼのようなものがあればいいと思う。痛みは残っても直視しないで済むなら、それで救われる感情もある。
「私」には生まれてからたった二時間で死んでしまった「姉」がいた。「タルトック(註:月のように丸い餅)のように色白の女の子だったらしい。八か月の早産で、躰はとても小さかったが、目鼻がはっきりして美しかった」と「私」は母親から聞いていた。
私は死の物語の中で育った。稚いけものの中でもいちばん無力な生きもの。タルトックのように真っ白で美しかった赤ん坊。その子の死んだ跡地へ私が生まれてきて、そこで育つという物語。
(単行本23頁より引用)
「私」は滞在することになった都市の博物館で1945年の春に米軍が空撮した映像を見る。そして1944年10月から六カ月あまりの間にその都市の95パーセントが破壊されたと知った。ふしぎなほど近しく、自分の生にも死にもよく似ているその都市に重ね合わせるようにして、「私」は一度死んで破壊されてから粘り強く復元してきた人として、死んでしまった赤ん坊の姉のことを考える。「しなないで しなないでおねがい」と母は赤ん坊に言っていた、その言葉をお守りのように宿して「私」ではなく「彼女」がこの都市へやって来ることを考える。
こうして、本書の主語が「私」から「彼女」へと変わっていく。「彼女」は都市の中心部を歩いていって四つ角に残された赤れんがの壁の一部を見ている。「爆撃で倒壊した昔の建物を復元する過程で、ドイツ軍が市民を虐殺した壁を取りはずし、一メートルぐらい手前に移したのだ。そのことを記した低い石碑が立っている。その前には花が手向けられ、たくさんの白いろうそくが灯っている」。「彼女」は著者の文学の言葉でしずかに語られる物語の中で育つ。文学の言葉は「私」の生と体を「彼女」に貸し与えるのだ。こうして「彼女」が歩く都市には霧がかかっているというのも忘れられない。70年前、ナチスドイツに破壊された街の廃墟を覆い隠す白いガーゼみたいな霧。
隠してはおけない、けれども剥き出しの傷(死)と対峙することはできない。だからこそ、白いガーゼで覆うような場所と時間が必要だった。「闇と光の間でだけ、あのほの青いすきまでだけ、私たちはやっと顔を合わせることができる」とあるように、「私」と「彼女」が会えるのは、死という傷跡を覆うそっと一枚置かれた白いガーゼによって作られるような、うすくて、かるい、あるかないかの白い時空でだけだ。この白いガーゼのようなものの役割を、ハン・ガンの文学の言葉は果たしている。著者の言葉がガーゼの役割を担って「彼女」を存在させている、哀悼のように。
この本は文学によって可能になる、そういう奇跡的な感触を捉えている。余白までうつくしい本だった。三つの大きな章とその中にちらばる短い散文を私は繰り返し読む。同時に私が小説を書く時の手つきについて考える。小説を書き始める時、私は私を空白にして、別の「何か」や「誰か」に時間を託す。私の人生の時間の大半は空白なのだと思う。だからなのかSNSで言いたいことがほとんど無い。
今年になって読めないくせに韓国語版の本書を手に入れた。タイトルは『흰』とあった。