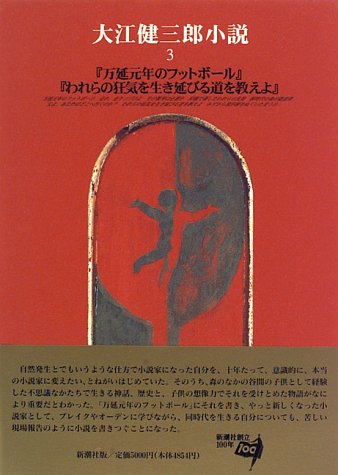死ぬことは、とても大変なことなのだと思う。そのくせ、自分が死ぬ時には魂がぽろっと崖から転げ落ちるようにあっけなく死ぬんじゃないかと思っている。楽をしたい。それはたぶん自分の中にある本当の地獄に向き合うのが恐ろしくて耐え難いからだ。死に至るまでの思考の厚み、自身が引き裂かれるほどの葛藤、そういうものをもし言葉にするとしたらその総量はとてつもない。小説の中に死を書いてそれに説得力(死ぬことの手触り)を持たせるとしたら、そこに必要になる言葉の数もまたとてつもない。『万延元年のフットボール』を読んで、そういうことを考えていた。今の私は自分の地獄を表す言葉を持ってはいない。
大江健三郎『万延元年のフットボール』(『大江健三郎小説3』新潮社、1996年所収)
語り手「僕」こと根所蜜三郎とその妻である菜採子。ふたりの間に頭に腫瘍を持った子供が生まれた。そのことを受け止めきれずに養護施設に入れてしまったことが、この夫婦にとって大きな葛藤になっている。そこへアメリカから蜜三郎の弟である鷹四が帰国する。彼は安保闘争で傷つき、己のうちに「地獄」を抱えている。そんな彼らが故郷である四国の森の中の集落に戻ると、曾祖父の弟が首謀者であったという万延元年の一揆を百年後の作中現在に繰り返すように、スーパーマーケットの略奪という暴動が起きる。
雑な把握の仕方なのかもしれないが、この作品からは二種類の人間の有り様が浮かんでくる。ひとつは「己の内側に抱えた地獄を正面から引き受けて戦い乗り越えていくタイプの人間」で、もうひとつは「そういう地獄の存在などついに見定められずにもっと薄暗く不安定で曖昧な現実生活をおとなしく生き延びていくタイプの人間」だ。前者を鷹が、後者を蜜がそれぞれに受け持っているように読んだ。
「歴史は繰り返す」とはよく言う。万延元年の一揆が百年後に別の形を持って繰り返される。ではなぜ繰り返すのか、そのメカニズムとは一体どんなものなのか。鷹四のように地獄を引き受けて戦い乗り越えていく人間の持つ「暴力性」というか、感情の激しさが、一揆の契機となるのではないか。しかしその「暴力性」の効力はそれほど持続しないのだ。一揆のあとで来る敗北(ここに敗戦時の日本の様子も重なる)のあとで集落において人々に共有される感覚は「恥」である。蜜三郎が纏う雰囲気はこの「恥」の感覚だ。これは蜜三郎だけでなく、そこに住む多数の者に共有される感覚でもあって、そのおかげで何事もなかったかのように時は経ち人々は暮らすことができる。しかしその平穏な暮らしの中から「暴力性」が完全に消え去ることはない。「暴力性」は単に平和裏に忘れ去られるのではなく、集落の伝統である踊り念仏の「御霊」となって、いずれ目を覚ます時まで祭りの中に継承されていく。人々を「恥」の感覚に真正面から向き合わせて「憎悪」に転じさせる「暴力性」の目覚めが一揆や暴動といった歴史を繰り返す原動力になっているのではないか、そんなふうに考えた。
語り手「僕」こと根所蜜三郎は、自宅の庭に掘った穴のなかに尻を濡らして座り、異様な姿で縊死した友人のことや、養護施設に入れた頭に腫瘍を持って生まれた子供のことを考える。なぜ、どうして? と呪いたくもなる運命に「僕がきみたちを見棄てた!」と叫びたくもなる、そのくせ「僕」の胸の内に本当の地獄はない。というか、己の内側に巣食う「地獄」に真正面から向き合うことをしないで済ませている。穴のなかで無意識に自身を生き埋めにしようとしていたと思い至るも、穴のなかから見上げた赤い、地獄絵の炎に似たハナミズキの葉裏に「優しさ」を見出して慰められる「僕」は結局、自死することはない。対極の存在と言える鷹四は激しい感情を爆発させ、己の内側の地獄を戦った末に自死する。弟の地獄を理解できなかった蜜三郎は、子供のころから曾祖父の弟(万延元年の一揆の首謀者)にヒロイックな抵抗者の光背をおわせたがる弟に反発していた。「本当のこと」を知った時、蜜三郎は自分の地獄に向き合うことをしない自分の弱さを発見する。
――そうだ、きみは本当の事をいった、と僕は死の時の鷹四を見つめた数かずの家霊たちの眼に、いまは自分を四方から見つめられたまま屈服して認め、そのような惨めな自分自身の全体をくっきりと認識した。僕は自分を異様なほどにも無力に感じ、その無力感は寒さの感覚ともども加速度的に深まり、底なしに深まった。僕は憐れっぽい音を立てて口笛を吹き、マゾヒストじみた最低の気分でチョウソカベを呼びよせようとしたが、それが訪れて倉屋敷を崩壊させ僕を生き埋めにするということは当然おこらない。(238頁より引用)
「僕」は生き埋めにならない。底なしに深まった無力感、自身の弱さ、「恥」のゆえに地獄絵の「優しさ」に慰められながら、人生のつづきをただ生き延びていく。
自覚するかどうかは別として、たぶん大勢の人間たちの生き方はこうなのだろうと思わせられた、そして読みながらそのことにも苦しさを覚えた読書体験だった。
――おれたちの再審はすなわちおまえの審判だ!と舞台の上の鷹四が脣の肉の吹っとんで単なる赤黒い穴ぼこのような口を大きく開き憎悪と共に勝ち誇って叫ぶ。
(218頁より引用)
*
ちょうど本書を読んでいた時に大江健三郎氏の訃報に接した。本当は別のブログ記事を用意していたのだけれど、やはり『万延元年のフットボール』について新たに書くことにした。それがただ生き延びている自分が文学というものに誠意を込めて、ひっそりとできる哀悼の意の表し方なのだと思う。ご冥福をお祈りいたします。